【1】RK Musicが配信アーカイブ動画に関して持っている権利
MAP 今ココ
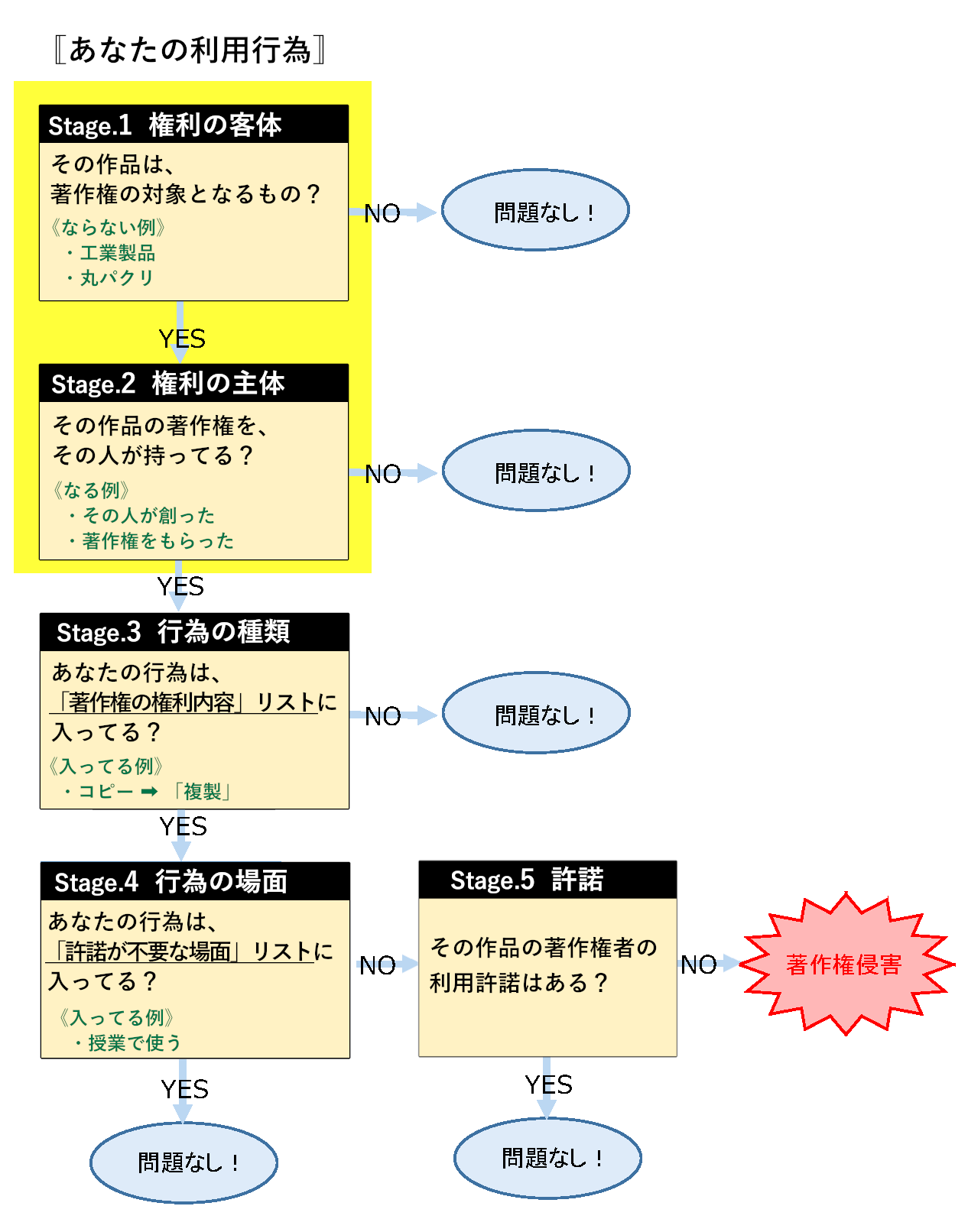
〚Stage 1,2〛誰が・何に・権利を持っているか?
「配信アーカイブ動画はどんな著作物で、それに対して誰が何の著作権を持つか」
…は、実は意外と複雑な問題です。
(この記事では詳細な説明は省略します。)
ネット上で
[切り抜き動画 著作権]
…と検索すると、ほとんどのページで
「動画は著作権で保護されている」
「動画は※1『映画の著作物』として著作権で保護されている」
「動画は※2映像著作物として著作権で保護されている」
…と書いてあります。
特に理由の説明がないものが大半です。
※『映画の著作物』について
著作権法は、著作物のカテゴリーを『言語』『絵画』『音楽』など列挙していて、そのなかに『映画の著作物』というカテゴリーがあります。
これは、映画館で放映される劇場映画だけを指すものではなく、広く《画像・画面を連続的に表示することで動いているように見える表現物》全般を指します。
動画は『映画の著作物』に区分されます。
ですので「動画が著作権で保護されるか」という問題は、ごく大雑把に言うと「著作権法が保護する『映画の著作物』にあたるか」の問題だと言い換えられます。
裁判例に「映像の著作物」という言葉が登場したことがあります。
それを意識してか、
『映画の著作物』にあたらなくても、著作物一般のなかの「映像の著作物」(あるいは「映像著作物」)として保護される場合がある
と説明するサイト等があります。
これは誤解を招く表現であるように思いますので、解説します。
著作権法2条3項の「映画の著作物」
著作権法では、「映画」「映画の著作物」という言葉が異なった意味で使われています。
この条文を観るとわかります。
著作権法2条 3項
この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
映画のほうは、皆さんが「映画」と言われてイメージする、映画館で放映されるアレです。
一方、「映画の著作物」が指すのは、もっと広い、〈画像を連続で映すことで動いているように見せる表現〉という内容です。
ややこしいから「映画の著作物」なんて言い方ではなく「動画の著作物」とでも書いてくれれば良いのに…。
なぜこんな規定のしかたになっているかというと、旧著作権法を改正する際に、旧著作権法で
活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ製作シタル著作物
と定めていた部分を
1. 「活動写真術」を「映画」という言葉に置き換える
➥「映画または映画と類似の方法により製作する著作物」
2. 「製作方法」ではなく「表現の効果」に置き換える
➥「映画または映画の効果に類似する~著作物」
3. 映画に関する規定の全ての箇所で「映画または映画の効果に類似する~著作物」と定めるのでは長ったらしいので、
①著作権法の最初のほうに「映画の著作物」には「映画の効果に類似する~著作物」も含むと書いておいて(2条3項)、
②それ以降は短く「映画の著作物」とだけ書く
…という工程で改造したからです。
ともかく、著作権法2条3項によれば、
「映画の著作物」という文言は、映画 だけでなく、広く〈画像を連続で映すことで動いているように見せる表現物〉を含む固有名詞です。
そういうわけで、固有名詞だよということを強調するために映画の著作物と書きます。
著作権法16条や29条の「映画の著作物」
しかし、さらにややこしいことに、著作権法のなかで
「映画の著作物は~」と定める規定のなかには、劇場映画のことだけしか想定していないものがあります。
というのも、その条文を作った当時には、PC・スマホはおろか、家庭用のビデオカメラもなく、動画での表現物といったら実際には劇場映画しか存在しなかったのです。
(ちなみに、映画が最初に著作物と認められたのは昭和6年です(昭和6年6月1日法律第64号)。
この当時は「映画」という言葉すらなく、「活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ製作シタル著作物」という規定でした。)
そんな時代で、さらに、著作権法16条や29条は、劇場映画界隈の要請を受けて作られたものです。
時代は進み、劇場映画以外の動画コンテンツがたくさん生まれました。
そうなった現在、劇場映画固有の事情を考慮して作った16条や29条の「映画の著作物は~」という規定を動画全体=映画の著作物の一般的ルールとするのは不適切です。
そのような場合には、これらの規定は「映画の著作物」という文言を使っているものの、映画の著作物すべてを対象とするものではない、と解釈することになります。
このように、
・2条3項の定義する映画の著作物
・16や29条の対象とするもの(条文で「映画の著作物」と表現されているもの)
との間にギャップが生じたとき、表現上どのように区別したら良いでしょう?
その表現方法は2つあります。
【表現方法1】 「映画の著作物」=映画の著作物 ≠16条・29条の対象
(2条3項優先パターン)
●著作権法の話で映画の著作物と言う場合は、2条3項の映画の著作物 =〈画像を連続で映すことで動いているように見せる表現物〉を指す。
●16条や29条は映画の著作物全体に適用されそうな書き方をしているが、映画の著作物であっても16条や29条が適用されないものがある
【表現方法2】「映画の著作物」=16条・29条の対象 ≠映画の著作物
(16条・29条優先パターン)
●16条や29条の適用されるものこそを、映画の著作物と呼称すべきである
●16条や29条は適用されないが著作権法2条3項の対象となる〈画像を連続で映すことで動いているように見せる表現物〉たちを、別の名前で呼ぶ
一番上に載せた、以下の説明
『映画の著作物』にあたらなくても、著作物一般のなかの「映像の著作物」(あるいは「映像著作物」)として保護される場合がある
…は、【表現方法2】を採用して、かつ別の名前に「映像の著作物」や「映像著作物」という呼び名を使うものです。
ですので、この説明の言っていることは
16条・29条の対象ではなくても〈画像を連続で映すことで動いているように見せる表現物〉(=映画の著作物)は著作権法で保護される
という話であり、全くおかしなことは言っていません。
しかし、よくわからずに読むと、
〈画像を連続で映すことで動いているように見せる表現物〉=映画の著作物の他にも、動画に関して著作権法で保護されるカテゴリーがある
…と誤解しかねません。
読者の皆さんには、誤解することなく読んでいただきたいと思う次第です。
【表現方法1】と【表現方法2】どっちが正しいか?
さて、【表現方法1】と【表現方法2】のどちらを採用するべきでしょうか?
関連する裁判例があります。
劇場映画の制作過程でも、16条や29条をそのまま適用しては不都合な場面が存在します。
それが問題となったのが、劇場映画の制作過程で撮影したフィルムの著作権です。
この問題についての裁判例のうちの1つが、上の【表現方法2】を採用して、『映像著作物』という概念・用語を使いました。
(全文はwebにありませんが、次の判例評釈内で主要部分が引用されています。
(PDF)「判例研究 青森県三沢市市勢映画事件」長塚真琴, 著作権研究 No.21,1994
映画に使用されなかった撮影フィルムの著作権を『映画監督』と『映画製作会社』のどちらが持つか争われました。
『映画製作会社』は、撮影フィルムは完成しようとしまいと29条の指す「映画の著作物」だから、著作権はウチが持っている!と主張しました。
これに対して東京高裁は、以下のように判断しました。
(1)「映画の著作物」としての成立要件
・映画の著作物として29条によって映画製作者が著作権を取得するには、撮影のあと編集を経て著作物として認められるに足りる映画が完成することが必要である
(2)フィルムが『映像著作物』であること
・未編集のフィルムでも、創作性があれば『映像著作物』として著作権の対象となり、著作者が著作権を取得する
(3)『映像著作物』であるフィルムと「映画の著作物」との関係
・映画が完成したら、『映像著作物』は映画に「化体されその内容となる」結果、『映像著作物』の著作権は存在しない
・映画が完成前に打ち切られた場合でも、映画制作過程で『映像著作物』であるフィルムに対して編集などが行われて、打ち切られた時点のものに創作性があれば、製作者は(編集されたフィルムについて)著作権を取得する
(4)この事案のあてはめ
・本件では映画が完成していない
・本件のフィルムには『映像著作物』として創作性があり、『映画監督』が著作者であるから、『映画監督』が著作権を取得している
この裁判例の結論にも賛否がありますが、それはさておき、「映画の著作物」とは異なる『映像著作物』なる概念・用語を作ったことは専門家たちの間で肯定的に受け入れられなかったようです。
(私の手の届く範囲の教科書で、この概念を活用しているものはありませんでした。)
「映画の著作物」とは〈画像を連続で映すことで動いているように見せる表現物〉=2条3項の定める映画の著作物を指す、との前提の上で、映画の著作物全般に対して16条・29条が適用されるか、それとも適用されない場合があるかを議論しています。
そのことを受けてか、この裁判例のあと「映画の著作物」と区別する意味で『映像著作物』という概念・用語を使う裁判例はほとんど出ておらず、裁判所においても定着しなかったようです。
裁判例はどこにある?
裁判の判決書は原則的にすべて公開されています。
しかし、公開とは言ってもデータベース化されているわけではありません。
むしろ、原則的にデータベース化されません。
民事裁判であれば、第一審のあった裁判所(最初に訴訟提起された裁判所・著作権に関しては多くの場合東京地方裁判所)に50年間保管されています。
公開というのは、「第一審裁判所に行って申請したら閲覧できる」ということです。
裁判例はどうやって探す?
上記のシステムだと「どこの裁判所でこういう事件があったから判決を見たい」というニーズを満たすことはできますが、前提として「どこの裁判所でどういう事件があったか」を知らないと判決書を見ることができません。
また、いちいちその裁判所まで足を運ばなければなりません。
それでは「ある争点について判断した裁判例はどこに・どれだけあるか」等を横断的に調べることは困難です。
また、実務家には全国津々浦々で出される重要な裁判例を知っておきたいニーズがあります。
そこで、重要な裁判例をピックアップして収録・提供するサービスがあります。
そのようなサービスには、公的機関(裁判所)が行っているもの・民間の出版社が行っているものがあります。
どちらも、古くは「ピックアップした裁判例を収録した雑誌を発行する」というスタイルで始まりました。
裁判所が行っているものは、重要な最高裁判例を収録する「民集」「刑集」、重要な高裁判例を収録する「高民集」「高刑集」などです。
月ごとに法曹会から出版されています。
民間の出版社が行っているものは、「判例時報」「判例タイムズ」などのほか、分野ごとの判例雑誌があります。
このような紙媒体のサービスが、時代とともにネット上のデータベースサービスに進化しました。
裁判所のデータベースサービスは「裁判例検索」です。
無料で利用することができます。
民間データベースサービスは
・D1-law(第一法規)
・LEX/DB(TKCローライブラリー)
・LLI(「判例秘書」など 株式会社LIC)
・WestLaw(トムソン・ロイター)
…などがあります。
月・年単位の契約で、高いです。
自治体によっては、これらの民間サービスを契約したうえで図書館等で無償で利用させてくれる場合があります。
私の住んでいる地域の図書館では、D1-lawのみ利用できます。
そういうわけで、私が調査できる裁判所の裁判例検索とD1-lawに載っているものだけです。
判決文のなかで『映像著作物』という言葉を使っている裁判例は、裁判所webサイト裁判例検索およびD1-lawに収録されているものは、以下の4つです。
※ 判決文のなかには、原告・被告の主張が要約して記載されます。
今回問題としているのは「裁判所が『映像著作物』という言葉を使用したか」ですので、主張の部分でのみ『映像著作物』という言葉を使用している裁判例は除外しました。
第3 争いのない事実等
竜の子プロ事件 東京地判H16.7.1 平成15(ワ)19435
被告バンダイビジュアル株式会社は、映像著作物の企画、製作並びに映像著作物の複製物の製造、販売及び輸出入などを業とする会社である。
一般に、本件ビデオ等のような映像著作物の製作に関わるカメラマンの拘束料は、一ヶ月あたり55万円から75万円であった
東京高判H13.12.12 平成12(ネ)2036
第3 前提となる事実
東北新社事件 東京地判平成13年7月2日 平成11年(ワ)17262
被告バンダイビジュアルは、映像のソフトウェア等の映像著作物の製造販売等を目的とする会社である(弁論の全趣旨)
原告は、テレビ映画の企画、製作及び販売並びに映像著作物の版権管理及び利用開発を業とする株式会社である(映像著作物の判検管理・利用開発の目的につき弁論の全趣旨)
東京地判H23年11月29日 平成23(ワ)17393
以上の4つとも、すべて「劇場映画以外のもの」というニュアンスで『映像著作物』という言葉を使っているものの、「『映画の著作物』ではなく『映像著作物』だ」という趣旨では使用されていません。
ですので、『映画の著作物』と区別する概念として『映像著作物』という言葉を使用している裁判例は(少なくとも上記データベース上は)ない、と言えるでしょう。
以上をまとめると、現在の著作権法に関する話のなかでは【表現方法1】が優勢であるようです。
ですので、専門家ではない私たちがイメージを掴むには、とりあえず下のように理解しておくのが良いと思います。
●著作権法上、〈画像を連続で映すことで動いているように見せる表現〉は映画の著作物として保護されている
●「映画の著作物」について定める条文(16条・29条など)は、劇場映画を念頭に置いてる場合が多く、適用すべきでない場合もある
私の感覚としても、【表現方法1】のほうが適切であるように思います。
理由は、2条3項が”定義規定”であることです。
著作権法2条は、
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…で始まり、40個近い用語を”定義”しています。
その中の1つである3項が、
「映画の著作物」には劇場映画だけでなく〈画像を連続で映すことで動いているように見せる表現物〉が含まれる
…という風に定めています。
定義規定を無視しては、定義規定を置いた意味がなくなってしまいます。
また、条文上出てきて、客観的に共有されている用語ではない概念・用語を作って使いはじめると、個々人が微妙に違う意味で使いだして、かえって議論が混乱するのではないでしょうか。
(私が法律を勉強してきたなかで、そういう言葉の使い手ごとの意味の違いにたくさん苦しめられてきました。特に民事訴訟法で。)
実は、「ちゃんと言葉を使い分けるように法改正しよう」という話も公的な場所で検討されたそうです。
『著作権審議会』という文部科学大臣・文化庁長官の諮問機関(有識者会議みたいなもの)の中の『マルチメディア小委員会 ワーキング・グループ』が、平成7年に検討しています。
その報告書(web上で読めます)の関係する部分・8.映画に関する規定の見直しから一部引用します。
〈考えられる対応例〉
[A] 映画の著作物の範囲は伝統的な劇場用映画に限定するとともに、それ以外の文字、音声、画像等の情報が統合され全体として一つの創作的表現となっている著作物については、「視聴覚著作物」又は「マルチメディア著作物」のような新たな著作物の分類を別途設ける。
[B] 映画の著作物という分類を廃止し、より広い範囲の著作物を含む「視聴覚著作物」又は「マルチメディア著作物」のような新たな著作物の分類を設ける。
〈考察〉
現行法における映画の著作物の概念について、見直すべき時期に至っているとの意見が多かった。
その場合、基本的には、[B]のように映画の著作物の概念自体を改めるべきであるとの意見が多かったが、当面は従来の実務慣行等への影響に留意して、[A]のように映画の著作物の概念を維持しつつ、別途新たな分類を設けることが適当であるとの意見もあった。もっとも、今日、映画は当初から劇場公開以外にビデオ化等の利用を行うことを前提として製作されることが多く、また、ビデオによる上映も発達しつつあることを考慮すると、映画の著作物と新たな分類の著作物との区別が困難になることを考慮する必要があると考えられる。
個人的には、そのとおり改正してくれよ!!!!という思いでいっぱいです。
上のようなネットの説明、本当に合っているでしょうか?
配信動画は、イラスト・配信UI・トーク音声・BGM etc.. さまざまなパーツが組み合わさってできています。
これらのパーツは、それぞれ単独で著作権で保護されています。
「動画」というパッケージに組み込まれても、個々のパーツの著作権たちが消滅することはありません。
たとえば、あるイラストが使用されている動画を違法転載したら、イラストの著作権の侵害にもなる、ということです。
そういったパーツ単位の保護を超えて、「動画」という一体の総合表現として保護すべきなのはどんな時でしょうか?
著作権法が保護するのは、創作的な表現です。
もし「動画」のなかに表れる創作的な表現が、全て個々のパーツの創作性に還元されるものであれば、パーツ単位で保護すればそれで良いじゃん、となります。
ですので、「動画」というパッケージそれ自体を保護すべき場合とは、それぞれのパーツ自体が持つ創作性・表現性を超えて、それらを組み合わせて、同じ画面内で時間経過に同期して動く「一つの動画」作品という表現にすることで(平たく言えばいっしょに動かすことで)新しい独自の創作性な表現が生まれていると言える必要があります。
ただ単にmp4やflvといった動画ファイル形式でYouTubeにアップロードするだけでは、その「動画」は『映画の著作物』として保護される条件を満たしていない、ということです。
たとえば、ある楽曲を音声に使用し、画面は黒一色で動かない動画」の形でYouTubeにアップロードしたとします。
これは、実質的には「YouTubeというサイトで再生できる楽曲音源」に過ぎません。
動画で使われている楽曲を音楽の著作物として保護するのは当然ですが、それを超えて、わざわざ動画として著作権で保護することにはならないでしょう。
この画面を「黒一色」から「1枚のイラスト」に変えてみましょう。
この場合も、楽曲を保護するのに加えて、イラストを絵画として著作権で保護すればそれで十分ですし、わざわざ「一体となった一つの動画」として保護するだけの創作的な表現が加えられているとも言えません。
では、イラストをスライドショーで切り替えたら?
画面内のイラストをぐるぐる回転させたら?
…と、どこから動画としての創作的な表現が生まれていると判断できるかが問題になるわけです。
さて、VTuber/singerの配信について、2D・3Dアバターが動くような配信であれば、アバターの動きによって創作的な表現が付加されていると言えるでしょう。
ただ立ち絵イラストが表示されているだけでなく、トークなどに際して身振り手振りで動き、表情が変わり、まるで相手と顔を合わせて喋っているように感じられることが配信の醍醐味になのではないでしょうか。
裁判例もそう考えているようです。
この事件は、
兎田ぺこらさんの配信動画のスクショに縄のイラストや「死ぬぺこ」という文字を加えたコラ画像ツイートが、ぺこらさんの立ち絵イラストや配信動画の著作権侵害となるかどうか問題となった事件です。
(以降この記事に度々登場するので、「兎田ぺこら事件」と呼びます。)
裁判所は、特に理由を説明することなく当然のこととして、配信動画は『映画の著作物』にあたると認めました。(東京地判令和5年1月31日(令和4(ワ)21198))
(なお、同じ事件についての知財高判令和5年3月9日(令和4(ネ)10100)では、何の著作物か特定することなく「著作物にあたる」とだけ判示されました。)
実は、上に書いた「ほとんどのページ」は、このようなアバターのある配信(あるいは実写YouTuberさんの配信)を念頭に置いているから、多言を要することなく、動画自体が著作権の対象となる・『映画の著作物』であると断定しているのです。
しかし、VESPERBELLの配信は、2D・3Dアバターを使用しておらず、上のようなVTuberの配信とは事情が大きく異なります。
VESPERBELLの配信動画のなかでも、配信UIやコメントなど動いているものはあります。
しかし、少しでも動けば『映画の著作物』としての創作性が認められるわけではありません。
動く部分が少ない、動きが小さい・単調である…等の理由で、裁判所が「『映画の著作物』にはあたらない」と判断した例もあります。
『映画の著作物』にあたるかが裁判上よく問題になるのジャンルは、TVゲームです。
TVゲームであっても、画像・画面を連続的に表示することで動いているように見せて、それが創作的な表現であると認められるならば『映画の著作物』として保護されます。
この一般論は確立されています。
しかし、「たしかに動く部分はあるが、その程度の動きでは『映画の著作物』にはあたらない」と判断した裁判例が複数あります。
(※なお、仮に『映画の著作物』にあたらなかったとしても「プログラムの著作物」として保護される可能性はあります。)
そのTVゲーム内の動きが『映画の著作物』と言える程度かどうか争われた、有名な裁判例を紹介します。
●『映画の著作物』といえる創作性がないとされた例
・「三國志Ⅲ」事件 控訴審(東京高判平成11年3月18日 平成7(ネ)3344)
…シミュレーションゲーム
・「猟奇の檻」事件 控訴審(知財高判平成21年9月30日 平成21(ネ)10014)
…マップ移動とかもある紙芝居系エロゲー
●『映画の著作物』といえる創作性があるとされた例
・「ときめきメモリアル」事件 控訴審(大阪高判平成11年4月27日 平成9(ネ)3587)
…恋愛シミュレーションゲーム
・「神獄のヴァルハラゲート」事件 (東京地判平成28年2月25日 平成25(ワ)21900)
…ソシャゲ(アクションではない、割とポチポチゲー)
映画の著作物の定義は
著作権法2条 3項
この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
です。
かつて、ゲームはプレイヤーの操作によって画面の表示・ストーリー展開などが変わるので、『固定されている』とは言えないのでは?
…という点が争われました。
この議論は、「ゲームも『固定されている』と言える」で決着が付いています。
その理屈はだいたいこんな感じです。
・「プレーヤーの操作で画面の表示・ストーリー展開がどう変わるか」はプログラムによって予め決まっていて、膨大だが理論上は有限な映像表示の分岐として固定されている。
・プレーヤーの操作に応じて分岐の中から特定のものを抽出して表示しているに過ぎず、表現物の内容をプレーヤー自身が変更しているわけではない。
・したがって、ゲームとして完成した時点で、制作者によって物に固定されていると言える。
そもそも、この「固定されている」という要件が条文に入れられているのは、生放送を除外するという意図であるそうです。
ですので、この要件はあまり厳密に捉える必要がない、という理解が一般的なようです。
ですので、VESPERBELLの配信動画が『映画の著作物』にあたるかどうかは、しっかりと検討する必要があるトピックです。
また、仮に配信動画それ自体が『映画の著作物』にあたらず著作権で保護されないにしても、「パーツの著作権」は保護されていますから、パーツの著作権の侵害が問題になります。
それに対応して、結論【1】で書いた、RK Musicが持っている「何らかの著作権のようなもの」もいくつかのパターンが想定できます。
複数のパターンのうちどれに該当するかは確定できないけど、どれかには該当する可能性が高いので、いずれにせよ著作権のようなものを持つ可能性が高いと言える
という構造です。
以下、パターンの内容を説明します。
権利パターン
「どの」著作物の「どんな」権利を持っているか、のパターン
RK Musicは(ⅰ)に該当する可能性が高く、仮に該当しないとしても(ⅱ)に該当する可能性が高い。
(ⅰ)著作権を持っているパターン
RK Musicは、以下のうち1つまたは複数の著作権を持っている
ア. 動画自体
イ. 動画のパーツである
①イラスト
②UIデザイン
③ヨミとカスカのトーク
(ⅱ)著作権を代理行使する権限を持っているパターン
RK Musicは、ヨミ・カスカが持つ
ア 動画自体またはイ③トークの著作権を代理行使する権限を持つ
「どうやって」権利を手に入れたか、のパターン
(ⅰ)著作権を持っているパターン
《発生タイプ》…著作権がはじめからRK Musicのもとに発生した
《移動タイプ》元の権利者から契約によって著作権を譲り受けた
①イラスト:ろるあママから
②UIデザイン:Moti氏から
③トーク:ヨミとカスカから
(ⅱ)著作権を代理行使する権限を持っているパターン
RK Musicは、ヨミ・カスカから著作権の代理行使を委任された
権利を手に入れている可能性が高いと言える理由
①イラストや②UIデザインなどの制作契約においては、制作契約の中の著作権条項・あるいは製作契約とセットで締結する著作権契約で、
「本契約に基づいて制作・納品された成果物の著作権を、RK Musicに譲渡する」
…と規定されるのが一般的です。
これは(ⅰ)《移動タイプ》の契約にあたります。
RK Musicとろるあママ・Moti氏の契約でも、著作権を譲渡する規定があるはずです。
↓のツイートの左下を見て下さい。
©RK Music とあるのが見えるでしょうか。
この©マークは「Copyrignt」=著作権のマークです。
つまり、©RK Musicは、RK Musicが著作権者だよという表示です。
ごく一部の国では、著作物として保護されるためには©マークを付ける必要があります。
(1989年まではアメリカもそうだったため、多くのものに付けられていました。)
©マークを付けるのに手続や認証は要りません。
個人が勝手に付けることができます。
ですので、©RK Musicという表示があっても、RK Musicが著作権者であることは保証されません。
しかし、過去に「著作権が消滅しているのに©マークを表示することは不正競争防止法に反しないか」と争われた裁判がありました。
不要なリスクを避ける企業法務としては、自身に著作権があると証明できる客観的な証拠がない限り、©マークを付けることはしないでしょう。
ですので、このヨミとカスカの立ち絵について、少なくともRK Musicは自身に著作権があると確信しており、それを根拠づける客観的な証拠、すなわち、ろるあママとの契約書の中の明文規定が存在する可能性が高いです。
一緒に載っているKMNZも同様のはずです。
RK Music以外のVTuber/singer事務所の運営会社は、どのパターンの契約を行っているでしょうか?
契約書が公開されていないので通常であれば知ることはできません。
しかし、例外的に公的に知ることが出来る場合があります。
それは、運営会社が裁判をして、その判決が公開された場合です。
VTuber/Singerの著作権に関連する判例をディグってたら、ホロライブとぶいすぽだけ出てきました。
ホロライブ
兎田ぺこらさんの公式イラストの著作権について、上に挙げた「兎田ぺこら事件」では
兎田ぺこらさんの配信動画のスクショに縄のイラストや「死ぬぺこ」という文字を加えたコラ画像ツイートが、ぺこらさんの立ち絵イラストや配信動画の著作権侵害となるかどうか問題となった事件です。
証拠(甲12、14ないし16)及び弁論の全趣旨によると、控訴人(カバー株式会社)キャラクターは、控訴人が、控訴人キャラクターに係る著作権等の権利が控訴人に帰属することを条件とし、外部のイラストレーターに委託して制作させたものであると認められる~(略)~
知財高判令和5年3月9日(令和4(ネ)10100)
原告(カバー株式会社)は、原告イラスト及び原告動画の著作権を有している(甲12及び弁論の全趣旨)。
東京地判令和5年1月31日(令和4(ワ)21198
と判示した裁判例があります。
カバー株式会社が(ⅰ)イラストの著作権を持つことは裁判で確定されていますね。
《発生タイプ》か《移動タイプ》かは微妙なところです。
1つ目の裁判例を見ると、カバー社は「著作権等の権利が控訴人に帰属することを条件とし」てイラスト制作契約をしているとあります。
著作権を譲渡するのではなく、わざわざカバー社に「帰属することを条件とし」た契約、という体裁を取っているあたり、カバー社としては《発生タイプ》にしたいという意志が見て取れます。
しかし、会社に始めから著作権が生じるかどうかは、著作権法の定めにあてはまるどうかで決まるものであり、カバー社とイラストレーターの合意で変えられるものではありません。
今回のケースだと、《発生タイプ:従業員》会社の従業員が業務として作った場合 に該当する必要があります。
(《発生タイプ:従業員》についての説明は、↓の【余談】ちょっと詳しい説明を参照してください。)
兎田ぺこらさんのイラストを作成した憂姫はぐれ氏はフリーランスで活動されており、《発生タイプ:従業員》に該当するかは微妙なところです。
なお、雑誌記事について、フリーランスのライターが編集メンバーに加わって書いた記事は《発生タイプ:従業員》にあたると判示した裁判例があります((東京地判平成7年12月18日(平成6(ワ)9532))。
だからといって、「フリーランスでも従業員にあたる」と一般化することはできません。
編集チームとして作業するケースとイラストレーターに委託するケースでは「どれだけ発注企業の組織のパーツとして活動するか」に大きな差がありますので、一概に論じることは出来ないでしょう。
ぶいすぽ
証拠及び弁論の全趣旨によれば、~(略)~令和5年4月11日付け業務委託基本契約~(略)~に基づき、本件イラストの著作権がその発生と同時に原告に移転した事実がそれぞれ認められる。
大阪地判令和5年9月25日(令和5年(ワ)5818号)
こちらは「移転」と書かれていますので、明確に《移動タイプ》ですね。
③トークについても、RK Musicとヨミ・カスカとのマネジメント契約のなかで規定されているはずです。
「ヨミ・カスカの名義で行った配信動画についてヨミ・カスカに生じる一切の著作権を、RK Musicに譲渡する」
=(ⅰ)《移動タイプ》の契約
「~一切の著作権はRK Musicに帰属することを確認する」
=(ⅰ)《発生タイプ》であることを確認する規定
「~一切の著作権の行使をRK Musicに委任する」
=(ⅱ)の契約
ですので、RK Musicは、
(ⅰ)ア.動画自体または①イラスト ②UIデザイン ③トークの著作権を、仮に《発生タイプ》に該当しなかったとしても《移動タイプ》によって持っている可能性が高い
(ⅱ) ア. 動画自体 または③トークについては、仮に(ⅰ)で著作権を取得していなくても著作権を代理行使する権限を持っている可能性が高い
と言えるのです。
そして、これらの権利のどれか一つを持っていれば、切り抜き動画に対して「それを使うな」と言えます。
ですので、実質的に切り抜き動画自体の削除を要求できる、ということになります。
(公式イラストや配信UIを映していない切り抜き動画・トークを使っていない切り抜き動画は考えられませんよね。)
(「はずです」と言える理由など、もう少し詳しい話は↓のアコーディオン内。)
ⅰ. 著作権を持っているパターン
ア.動画自体 とイ.パーツ①~③ を区分けして考えている理由
アとイの区分けをしているのは、
ア. 動画自体が1つの作品として著作権の対象となるか? 断言できないためです。
(このことは上の +【補足】ちょっとだけ説明 で説明しています。)
ですので、ア. 動画自体 イ. パーツ どちらについても検討する必要があるのです。
そして、RK Musicは少なくともイ①~③どれかの著作権を持っている可能性が高いです。
以下、ア. イ①~③について、「誰が」著作権者になるか検討します。
●著作権者を決める原則ルール:「作った人」=「著作権者」
【Part 1】に書いたとおり、著作権法では
「実際に頭と手を動かして作った人」=「著作権者」
というのが原則です。
ア. 動画自体を作ったのが誰かは難しい問題です。
動画パーツの①イラストはろるあママが、②配信UIはMoti氏が、③トーク内容はヨミとカスカが作っています。
一方、RK Musicは法人という「概念」ですので、物理的に動かす「頭」や「手」がありませんから、「実際に頭と手を動かして作った人」にはなりえません。
そのため、原則ルールではRK Musicに著作権はありません。
●「作った人」≠「著作権者」になる例外ルール
例外ルールは、
《発生タイプ:従業員》…会社の従業員が業務として作ったもの
《発生タイプ:映画》映画の制作会社に雇われた映画監督が作った映画
《移動タイプ》著作権を譲り受けた場合
の3つがあります。
(詳細は【Part 1】[Q5] +【補足】例外は3タイプある―身近な例をご覧ください。)
RK Musicが《発生タイプ:従業員》《発生タイプ:映画》に該当するかは微妙なところです。
(私の考えは別の記事で説明します。)
仮に《発生タイプ》に該当しなかったとしても、本文に書いてあるとおり、RK Musicは《移動タイプ》「著作権の譲渡契約」を結ぶことによって動画のパーツの著作権を取得している可能性が高いです。
「可能性が高い」と言える理由は、以下の2つです。
- コンテンツ制作契約やマネージメント契約を結ぶにあたってはセットで著作権の譲渡契約を結ぶのが慣行として根付いており、テンプレートになっている
- この契約を結んでおかないとRK Musicとクリエイターとの間での権利処理が面倒になるので、ちゃんとした大企業のグループ会社であるRK Musicの法務スタッフが見逃すわけがない
コンテンツ制作契約では、「著作権譲渡契約」の代わりに「利用許諾契約」が結ばれることがあります。
・制作を依頼する人のことを発注者(注文を発する人)
・依頼を受けて制作する人のことを受注者(注文を受ける人)
…と言います。
利用許諾契約とは
「利用許諾契約」は、
・著作権は受注者(=作った人)のところに残したままで(=著作権の譲渡はせず)、
・受注者が発注者に「成果物を利用して良いよ」と約束する
…という契約です。
本契約に基づく制作物の著作権は○○(作った人)に帰属し、○○(作った人)はRK Musicがxx条に定める範囲でこれを利用することを許諾する。
著作権譲渡契約との違い
発注者が使える範囲
・著作権譲渡:完全に好きに使える
・利用許諾 :利用許諾契約で定めた範囲だけ
発注者は無断使用者に対して文句を言う権利があるか
(切り抜き動画はまさにこの話です)
・著作権譲渡:ある。裁判を起こせる。
・利用許諾 :言えない。
このように、基本的に
・著作権譲渡契約は発注者(RK Music)に有利
・利用許諾契約は受注者(作った人)に有利
…だと考えられています。
これまで実務上は著作権譲渡契約が一般的だったようです。
しかし、「著作権を譲渡したコンテンツが自分の思いと異なる取り扱いを受けた」と発注者が不満に思うケースが現れるなかで、クリエイターに著作権に関する認識が広まり、「利用許諾契約にしたい」という考える人が出てきた…という感じみたいです。
RK Musicは、どっちだ?
おそらくRK Musicは「著作権を譲渡する」と書いてある契約書を提示して、「作った人」に特に異論がなければその契約書にサインして、それが契約内容になっているでしょう。
(RK Musicには、最初から自分に不利な条件を提示するメリットはありません。)
もし「作った人」から異議が出たら、交渉、すなわち両者のパワーバランスで決まることになります。
上の +【補足】①イラスト が(ⅰ)《移動タイプ》である証拠 で書いた通り、RK Musicとろるあママの契約はおそらく「著作権を譲渡する」契約です。
配信UIをデザインしたMoti氏には利用許諾に拘る理由がありません。
(配信UIが「思ったのと違う」使われ方をする場面はそう多くないでしょうし、Moti氏自身が使用することもないでしょう。)
ヨミとカスカも、著作権譲渡か利用許諾かについてそれほど拘りなく(意識せず)契約したのではないでしょうか。
よって、3者とも「著作権を譲渡する」契約であり、配信パーツの著作権はすべてRK Musicが持っている可能性が高い、と私は考えます。
RK Musicが「自分たちは《発生タイプ》に該当するから著作権が当然に自分のところに発生しているはずだ」と考えていたとします。
その場合でも、受注者との間で「どっちに著作権があるか」揉めることのないよう、確認の意味で
「本契約に基づく制作物の著作権はRK Musicに原始的に帰属する(ことを確認する)。」
と規定することが通常です。
この規定のある契約書にサインしている以上、受注者は後から「そんなつもりじゃなかった」と言えませんからね。
また、《発生タイプ》の中でも「映画」のほうの場合、契約書には
「○○(作った人)は著作者人格権を行使しない」
という規定を入れておく必要があります。
ですので、その際にまとめて書いておくことになるでしょう。
(RK Musicが《発生タイプ:映画》を前提に契約関係を構成しているという可能性は、それほど高くないような気がします。このあたりの実務はわかりません。)
ⅱ. 著作権を代理行使する権限を持っているパターン
仮にRK Musicが著作権を持っていなくても、ヨミ・カスカとの契約のなかで
「ヨミ・カスカは、配信アーカイブ動画に関する※著作権侵害に対する差止め・損害賠償等の権利行使をRK Musicに委任する」
と委任されている可能性が高いと考えています。
(※もっと包括的に「~著作権の行使」という風に定めている可能性のほうが高いでしょう。)
そう考える根拠は、RK Musicの二次創作ガイドラインにあります。
二次創作ガイドラインは
「RK Music」~(略)~二次創作全体ガイドライン~(略)~は、株式会社RK Music~(略)~または当事務所所属タレント自身が権利を有するコンテンツについて、二次的著作物制作者が利用できる範囲及びその条件を定めたものです。
本ガイドラインの範囲内にて創出され、公に発表された二次的著作物に対して、当社は権利主張を行わない方針です。~(略)~
禁止事項に抵触、あるいはその疑いがある「切り抜き」は、著作権侵害行為の対象として何らかの対処を行う場合があります。
本規約は予告なく変更することがありますので、常に最新の内容をご確認ください。
と定めています。
「タレント自身が権利を有するコンテンツ」について利用許諾のガイドラインを決めたり変更する権利を持っているのは、本来であればタレント自身のみです。
ですが、ガイドラインの規定によると、「タレント自身が権利を有するコンテンツ」についても、RK Musicがガイドラインを定め・変更し・違反に対して著作権に基づく対処を行うことができるようです。
RK Musicがそのようなことができるのは、権利者であるタレント自身からそのことを依頼されている場合です。
そのような依頼に基づかない限り、RK Musicは「タレント自身が権利を有するコンテンツ」については無関係な他人に過ぎません。
ですので、そのコンテンツについてRK Musicがどんなガイドラインを定めようと無意味です。
この委任契約によって、RK Musicは違法転載動画などに対して「消せ」と差止請求できるようになるのでしょうか?
委任に基づく代理行使
まず、「ヨミ・カスカに『本人に代わって権利行使すること』をお願いされているから」という理由では、RK Musicは、ヨミ・カスカの持つ権利を「代わりに」行使することはできないと考えます。
法律上の行為を他人に依頼することを、「委任」と言います。
民法643条に定められています。
「法律上の行為」にも色々ありますが、訴訟を含む権利行使については、委任できる場合・委任できる相手などが法律によって規制されています。
関連する法規制
・弁護士以外の者が法律事務を取り扱うこと➡禁止(弁護士法72条)
・訴訟行為を主たる目的とする信託➡禁止(信託法10条)
・著作物の著作権管理を目的とする信託・委任➡業として行うには登録が必要(著作権等管理事業法3条)
そのため、これらの規定に沿わない限り、「著作権者から契約で権利行使を委託されている」というだけでは、差止め請求権を行使できないと考えられています(東京地判平成14年1月31日 平成13(ワ)12516)。
RK Musicがヨミ・カスカから著作権の管理の委託を受けることは著作権等管理事業法2条1項の定める「管理委託契約」に該当し、RK Musicがこの契約に基づき管理委託することは同2項の「著作権等管理事業」に該当します。
この事業を行うには文化庁長官の登録を受けなければなりませんが(同3条)、RK Musicは登録を受けていません。
(登録者一覧は文化庁のwebページから見ることができます。)
したがって、RK Musicはヨミ・カスカとの委任契約を根拠として、代理人として著作権の権利を行使することはできません。
RK Music自身は差止請求権を持つか
RK Musicが、ヨミ・カスカとの間で「配信動画を独占的に利用できる」という契約を結んでいる場合を考えましょう。
無断で(違法に)転載動画が出回っては、RK Musicは動画の広告収入を得たり、動画をビジネスチャンスに繋げることが妨げられてしまいます。
それではRK Musicが「独占的に」利用できるという契約を結んだ意味がありません。
そのためRK Musicは自身の権利として(独占的に利用許諾を受けている地位から生じる権利として)違法転載動画を「消せ」と言いたい、すなわち差止請求権を行使したいはずです。
しかし、学説上「独占的に利用許諾を受けていたとしても、利用権者に固有の差止請求権は生まれない」と考えられています。
差止請求権は法律など特別の根拠があってはじめて認められる権利であるところ、著作権侵害に対して差止請求権を認める著作権法112条は、あくまで「著作権者の」権利として定めている、ということが理由です。
独占的な利用権は「著作権者と利用権者の間の約束事」に過ぎないから、利用許諾契約によって第三者に対する権利までは生まれない、というロジックです。
ですので、たとえRK Musicが動画について独占的な利用許諾契約を結んでいたとしても、それを根拠にRK Musicの差止請求権は生まれないことになります。
RK Musicはヨミ・カスカの差止請求権を代位行使できるか
民法には債権者代位権という権利が定められています。
- ある土地の所有者Aから、Bが土地を借りた。
Bは、その土地に家を建てよう思っている。 - その土地に、Cが勝手にキャベツ畑を作っていた。
…という事例を考えて下さい。
- Aは、土地の所有権に基づいて、Cに対して「勝手に土地を使うな、出ていけ」と言うことができる
- Bは契約に基づいて、Aに対して「土地を使用させろ(Cを出て行かせろ)」と言うことができる
- BはCに対して「土地を使用させろ」と言うことはできない
- AとBの契約は、あくまで契約の当事者であるAとBの2人に対してのみ効果が生じます。
- Cには契約の効果は届かないので、BはCに対する請求権を持ちません。
…という状況です。
AがBの要求に応じて、すぐにCを追い出してくれれば良いのですが、Aがズボラな人間だった場合、「Cを追い出したところで自分が使えるわけじゃないし、面倒だな」と放置してしまいます。
それではBが可哀想です。
このような場合に役に立つのが債権者代位権です。
債権者代位権は、
・BがAに対して「使用させろ」という権利を持っていることを理由に、
・Bに、
・『AがCに対して持つ「勝手に土地を使うな」と言う権利』を、
・Aに代わって行使する
…ことを認めるものです。
つまり、BはCに対して、Aの権利を代わりに行使することで「出ていけ」と言うことができるのです。
RK Musicが、
・RK Musicとヨミ・カスカが結んだ独占的利用許諾契約を根拠に、
・ヨミ・カスカの「転載動画を消せ」という権利を代わりに行使できるか
…という問題です。
これについて確立された判例はありません。
(東京地判平成14年1月31日 平成13(ワ)12516 は、認められる余地があるとしています。)
学説上は、これを認めるものが多いようです。
まとめ
RK Musicとヨミ・カスカが、
ヨミ・カスカは、自身が著作権を持つ配信動画/トークについて、RK Musicに独占的に利用を許諾する
という契約を結んでいた場合、独占的利用許諾契約を根拠として、著作権者であるヨミ・カスカの差止請求権を代わりに行使することができる(と考える学説が多いです)。
委任契約自体は、RK Musicが第三者(動画転載者)に対して差止請求権を行使できる根拠にはなりません。
ただし、こういう契約を定めることで、
「ヨミ・カスカは、RK Musicの求めに応じて、違法転載動画に差止請求権を行使する義務を負う」
ことを明確化しておくと、裁判において債権者代位権を立証する証拠となります。
そういう意味で、本文中の「ヨミ・カスカに委任されて代理行使する権限を持つ」という説明は不正確なのですが、実態としては「丸ごと全部お任せします、好きに使ってください」という合意のなかで委任契約と独占的利用許諾契約がセットで作用しており、これを「委任」とか「依頼」と表現したほうが読者の方に伝わりやすいでしょうから、便宜上この表記をとっています。


コメント